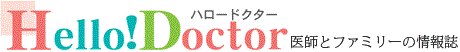「患者満足度No.1」の
病院を目指して

「救急からリハビリまで、専門的かつ包括的な医療を提供し、患者さま満足度No.1の病院をめざします」――。急性期医療の総合病院、関西電力病院(大阪市福島区)は、一般住民に広く門戸を開放し、安全で患者中心の病院▽地域医療との連携を推進し、開かれた医療への貢献▽責任と誇りをもって医療の向上に努める――の3つの柱を基本理念にしている。これからの地域医療をどのように進めていくのか。滝吉郎・同病院長にお聞きしました。(聞き手・池田知隆)
関西電力病院 滝 吉郎 院長
関西電力病院とは
病院の特徴を教えてください。
当院は1953(昭和28)年に関西電力健康保険組合直営病院として、主に職員の福利厚生を目的として7診療科、100床の病院として開設されました。その後、経営母体が健康保険組合から関西電力株式会社に変更され、1967(昭和42)年にここ福島区に移転してからは「地域医療への貢献」を目標に掲げ、社員以外の一般の住民の方々に広く門戸を開放し、診療の充実に努めています。関西電力関係の受診者は1%以下で、ほとんどが一般の患者さんです。現在、31診療科、病床数は400の総合病院です。日本医療機能評価機構認定病院、大阪府がん診療拠点病院でもあります。
病院診療における”強み”は。
大学病院で行われているような先進医療のすべてはできませんが、大学病院と同様の診療機能を有する病院(DPC特定病院群)に認定されています。循環器内科、心臓血管外科、脳神経内科外科、消化器内科外科、形成外科(切断肢対応)などは24時間の救急医療を行い、新型コロナウィルス感染症に対しては2020(令和2)年度から発熱外来を設置しています。
生活習慣病センターでは糖尿病内科を中心に循環器内科などいろいろな科と共同で糖尿病、高血圧などの診断、治療、生活指導を行い高い評価を受けています。
神経内分泌腫瘍センターでは神経内分泌腫瘍に対する専門的な診断、治療を行っています。遠方からたくさんの患者さんが来られています。
医師として
そもそもどうして医師に。
大阪ミナミの島之内(中央区)の生まれで大宝小学校、南中学校、府立高津高校までは大阪で過ごしていました。祖父は産婦人科を開業しており、父も産婦人科医で大学の教授を勤め、私はいわば3代目。幼いころから将来は医師になるものだ、と思っていました。母方の祖父の強い勧めもあり、また京都という町にあこがれもあったので京都大学医学部に進みました。
大学時代は?
大学では医学部の登山会に入り、ひたすら体を鍛えることに熱中しました。冬山の美しさに魅了され、冬季に北アルプス(雲ノ平横断)や南アルプス(北岳など白根三山縦走)などを経験しました。1974年12月、雲ノ平横断では、最終下山日に下山して留守宅本部や関係者に大変な心配をかけたことが思い出として強く残っています。
どうして外科を選ばれたのですか。
医学部登山会の先輩の多くが外科か整形外科なので、私も外科を選びました。兄がいて、脳神経外科に進み、僕も外科を選んだので、父はすこし不満そうでした。
消化器外科に魅かれたのは。
やはり、一番多くの臓器に対する手術が勉強でき、いわゆるジェネラリストになりたいというのが原因ですかね?最初はいろんなことをやりたいものだと思います。
京大病院第1外科で研修された後、どこへ。
その当時、赴任先に麻酔医がいないこともあり、1年は麻酔の研修をし、後の1年外科の研修を終えて赴任することになりました。同級生で話し合って赴任先を決めたのですが、一番遠いところに行くことになりました。岐阜市にある村上記念病院(現・朝日大学病院)です。都会の大きな病院ではできないことができ、いい経験になりました。
早くいろんな経験がしたいので上司の当直を変わってもらって当直をしていました。この病院に4年いたあと、大学から大学院の試験を受けて、研究室に入りなさいと呼び戻されました。

1974年12月 鏡平から槍穂高
どんな研究をされたのですか。
大学院では小澤和恵先生に師事しました。小澤先生は肝臓のミトコンドリアの研究で有名な方で、いろんな肝疾患、肝臓への手術などが肝臓のミトコンドリア機能に与える影響などを研究されていました。私も肝切除後のミトコンドリアの脂肪酸代謝や肝動脈塞栓術が肝ミトコンドリア機能に与える影響などをラットの肝臓を用いて研究しました。毎日ラットの肝臓からミトコンドリアを単離しその機能を測定していたのが楽しい思い出です。
その後、小澤先生が京都大学第2外科の教授になられて生体肝移植をめざすことになりました。当時は脳死肝移植を行うことが出来なかったので、先天性胆道閉鎖症の子供さんなどを救うための苦肉の策でした。ほとんどの医局員が移植の見学や研究に没頭し生体肝移植を成功させるために頑張っていました。研究室では毎週のように豚の肝移植実験を行っていたのもそのころですね。私は相変わらず麻酔担当でしたけど(笑)。
当時の肝移植では、アメリカのスターズル先生(コロラド大学、ピッツバーグ大学)、フランスのビスムート先生(パリ大学など)、ドイツのピッケルマイヤー先生(ハノーバー医科大学)の3人が世界的に有名でした。私はドイツのピッケルマイヤー教授のもとで肝移植を学ぶことになったのです。
ドイツでの2年間はいかがでしたか。
当たり前ですが、脳死肝移植はほとんどが緊急手術になります。ドナーが見つかれば直ちに準備にかからなければなりません。アウトバーンで車のラジオからピッケルマイヤー教授をさがす放送も聞いたことがあります。
そのころ、ピッケルマイヤー先生、助教授のリンゲ先生たちは年間100例ぐらい肝移植の手術をしていました。それでも長期休暇の時は1カ月もの長い休暇をとり、タイに行って休養しているのです。休暇の取り方という意味でずいぶん日本と違うと考えさせられましたね。日本の外科医などは病院から病院に勤務先を変えるときくらいしか長い休みは取れませんでした。その休暇も1週間くらいでしたからね。
移植の見学のため、ハノーバーの拙宅には次から次へと医局員がおとずれ、私は楽しいのですが、3歳と1歳の子供を抱えた家内に宿屋か居酒屋の女将のようなことをさせて本当に申し訳なかったなあと思っています。ただ、私たち家族も休みを取ることができたのでカナリア諸島など、あとになって簡単には行けないのでは?というところを訪れることも出来ました。
帰国後、京大に戻られてからは。
いよいよ1990年6月、京都大学で生体肝移植を行うことになりました。私もスタッフの一人として立ち会わせていただき、かねてから準備していた2例を立て続けに行いました。その2例の手術は大成功で、長年スタッフ全員がそのために努力してきたので、すごくうれしかったですね。 その後は音羽病院(京都市山科区)、神鋼病院(神戸市中央区)などで勤務し、1997年から北野病院(大阪市北区)に移りました。

北野病院、そして関西電力病院で救急部を作られたのですね。
当時、厚生労働省の初期臨床研修制度がスタートしており、研修病院では救急部での研修が必須になりました。北野病院はもともと救急指定病院であったのでこれを充実させるだけであったし、関西医大特殊救急部の中谷寿男教授のご高配で救急専門医の木内俊一郎先生をスタッフとして迎えることができたのであまり苦労なく、楽しく救急部を作り上げることが出来たと思います。
関西電力病院では救急部を一から立ち上げました。2002年に着任した時には救急指定病院ではありませんでした。救急を行うには多数の診療科が必要です。まず、切断肢接着で有名な形成外科医の高見昌司先生を招聘し形成外科を立ち上げました。その後、脳神経外科、心臓血管外科などを増設し現在に至っております。小児科と産科がありませんが、それ以外はフルに救急対応できる態勢になっております。高見先生の後を継いだ松末武雄先生ひきいる形成外科は現在でも24時間切断肢に対応し、大阪府内のみならず他府県からも救急患者さんが来られています。
関西電力病院外観 南側の堂島川対岸より撮影
臨床研究について
大学院ではミトコンドリアを中心に研究をしていたことは前述しました。私はすでに45歳を超えていましたが、外科のスタッフと共同で外科手術後の末梢血リンパ球のアポトーシスについてミトコンドリアの膜電位を中心に研究し、学会発表、英文の論文も手掛けました。伊能忠敬先生にははるかに及びませんが“四十の手習い!”と思いながら久しぶりの臨床研究にも没頭できたことはよい思い出です。
関西電力病院でも研究できれば良いのになあと思っておりましたが、関西電力病院総長(元院長)の清野裕先生(元京都大学糖尿病内科教授)のご尽力で2015年に関西電力医学研究所が設立されました。これは一般病院では虎ノ門病院、北野病院に次ぐ日本で3番目の研究所です。臨床をしながら研究もしたいという先生方には魅力的な病院ではないかと思います。
新型コロナの感染拡大時はいかがでしたか。
すでに院内感染対策チームがありました。大学病院などの大規模病院では即座の対応が難しかったようですが、当院ではすぐに対応できました。新型コロナ会議を毎週開き、発熱外来もすぐに立ち上げました。呼吸器内科だけでは対応は不可能だろうということで他の科でも分担して患者さんを受け持つなどチームを組んでスムーズに対応できました。
振り返ってみて、何か学んだことは
まずは感染対策チーム(ICT)をきっちりと整備しておかなくてならないことですね。当院では設備も比較的に充実し、ICUと各階に1室ずつ陰圧室がありますので比較的速やかに対策をとることができました。大阪府の要請にはほとんど応じることができたと思います。緊急時の医療材料などの備蓄については病院単体では限りがありますから、行政が対応すべき課題ではないか思います。
これからの地域医療について
これからの地域医療への課題は。
これから高齢化と少子化が進み、慢性期医療とか訪問看護への対応が求められていきます。急性期医療の病院として、そのような医療機関や訪問看護を担う人たちとの連携を取っていかなくてなりません。現在、訪問看護や訪問医療をしていませんが、それにも取り組んでいかなくてはならない時期が来ると考えています。いま、訪問医療の医師がとてもたくさんの患者さんを診ており、地方では医師が足りていません。都会でもやがてその対応に迫られてくると思います。
病院間の地域連携については。
当院は大阪市の「西部地区」(福島、此花、大正、西、西淀川、港区と北区の一部)の約20万人が対象で、郊外の中堅規模市の人口程度です。ここに400~500床の同様な診療科を有する急性期医療を行う総合病院が複数(JCHO大阪、日本生命、住友、千船、暁明館など)があります。その中でも特に充実している当院の診療科(血液内科、リウマチ・膠原病内科、希少がんに対する消化器外科、放射線治療科など)では、総合病院間の連携が実績をあげています。今後は大学系列の垣根を超えた連携の強化にも努めていきます。
また専門性を売りにしたクリニックの開業も相次いでおり、そのような専門診療医院・クリニックとの連携や信頼関係を築き、治療を終えた患者さんをできるだけ紹介元に返すようにしていきたいと考えています。
長く臨床の現場におられ、患者さんとの交流や思い出は。
何と言っても、手術をした患者さんが外来に来られ、にこにこしておられるのを見るのが一番の楽しみですね。以前勤務していた病院で手術した人が当院で治療を受けたいと私を訪ねて来られることもたびたびあります。段々と年を重ねると、かつて治療した患者さんとの再会は楽しみの一つになってきます。

これから医療を目指す若い人へのメッセージを
私の経験からですが、一度大学に戻って大学院で基礎医学を学んだことが後の医師人生に大きく影響しています。自分で英文の論文を書いた経験があるとそれまで英文の論文をうのみにしていたことがわかり、批判的に読むこともできるようになります。また、基礎医学の知識がなければ臨床の論文もきっちり理解することは難しいと思います。私は今でもサイエンスとネイチャーの目次には目を通し、興味ある論文は読むようにしています。
若い先生方には短い期間でもよいから一度は研究室に身を置いたほうが良いと思います。また、その時にしか留学をして海外で暮らすチャンスはあまりないと思います。ドイツへの留学は私の一生の中で忘れがたい楽しくもあり、ほろ苦いようなかけがえのない体験でした。ぜひ、皆さんにも経験していただきたいものです。
若い外科系の医師には“患者さんにメスを入れさせてもらうのだから内科の先生に負けないくらいの勉強をしなさい”と常々激励しています。仕事ばっかりしろとは言いません。休みの時はしっかり休み、ここぞというときには集中力をなくさず、ちゃんとやってもらいたい。そして臨床医であれば、患者さんやご家族となんでも話ができるような普通の常識やコミュニケーションする力が求められていますね。
滝 吉郎 (たき よしろう)院長経歴
1951年8月 大阪市生まれ
1976年3月 京都大学医学部卒業
1976年4月 京都大学附属病院第一外科入局
1978年4月 岐阜村上記念病院(現、朝日大学病院)外科勤務
1982年4月 京都大学大学院医学研究科博士課程入学
1987年8月~1989年9月 西独フンボルト財団より
奨学金授与 西独ハノーバー医科大学にて臨床研修
1990年4月 音羽病院外科勤務(医療法人社団洛和会)
1992年4月 神鋼病院外科勤務(社会医療法人神鋼記念会)
1997年11月 田附興風会北野病院外科勤務 救急部兼任
2002年11月 関西電力病院外科勤務
2006年 4月 関西電力病院副院長
2021年 4月 同院長(現在に至る)