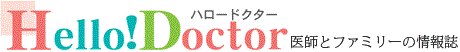ものたちの聲
第三十回(最終回)
「 わが父母」
歌 人 道浦 母都子
私の両親は、引き揚げ者です。「引き揚げ者」といっても、解らない方が多いでしょう。第二次大戦後、国外から引き揚げて内地へ帰ってきた人たちをいいます。
「引き揚げ者」の言葉もすでに死語
となり引き揚げ者の父母ニッポンに死す
道浦 母都子
私は、上のような一首をつくっています。
「引き揚げ」の大変さは、何度も何度も、聞かされました。両親は、ソウルで見合いをして、今の北朝鮮、感興の町で、終戦を迎えたそうです。そこには、朝鮮窒素(現在の日本窒素)の大工場があり、父は、そこに勤めていたようです。その日から、両親は大変な思いをしたそうです。無蓋車で国境まで運ばれ、大きな河の前で降ろされ、そこが国境だと言われたと。
目の前には、大きな河。まだ幼かった妹を背負った母は、途方に暮れた。
それが・・・。一人の青年が現われ、橋を渡るとロシア兵に襲われる可能性がある。一晩、自分の家で隠れ、明日の朝早く、河を渡りましょう。父母たちは、その青年を信じ、一晩、彼の家の倉庫に眠り、翌朝早く、河を渡ったそうです。青年は胸近くまで、水に浸かりながら、次々と両親や家族を対岸まで、渡らせてくれました。
父が、「なぜ、こんなに親切にしてくれるのですか?」と尋ねると、青年は「日本の北海道で働いていたのですが、自分が朝鮮に帰るとき、盛大な送別会をしてくれ、嬉しかった。そのお返しです」と答えたそうです。しかも、「自分を信じてくれたのも、嬉しかったのです」の話でした。
両親は、南北朝鮮の国境にある河を渡り、そこから、釜山まで歩き続けたそうです。
この話は、何度も聞かされましたので、忘れることはありません。だから、戦後生まれの私は、その青年が、いなかったら、私も生まれていなかったのだと、心の底から感謝しています。

だから、でもありませんが、私には在日の韓国人、朝鮮人への異和感は全くなく、チマチョゴリを買って、着てみたり、毎年、冬になると、母がキムチを漬けるのを手伝っていました。
三十八度線の北に埋もれし日々を言い母がキムチを漬ける冬来ぬ
道浦母都子
ただ、私がテレビのドキュメントの仕事で、韓国に行くことになったとき、父から「あの青年をさがしてほしい」と言われたのは困りました。名前もわからない。しかも、北朝鮮の方だから、見つけられるはずがないのに。
やむなく、テレビのスタッフに頼み、板門点までは行きました。大きな河が流れていて、その向こうに北朝鮮の地が見えていました。
板門店を訪ねたる日の猛吹雪 脱北は人 脱南は風
道浦母都子
そのときの短歌です。凄く寒い日で、北を眺めるのがやっとのような日でした。でも、私は、その青年への感謝(というより、もっと大きな何か)をずっと抱いて生きてきました。
その青年が、いまだに生きていて、北朝鮮で、淡々と生活していると信じています。

※長く、このコラムをお読みくださった方々に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。
道浦 母都子(みちうら もとこ) 略歴
1947年 和歌山県生まれ。
大阪府立北野高等学校卒業。
早稲田大学文学部在学中に
短歌結社「未来」に入会。
近藤芳美に師事。
1972年 歌集「無援の抒情」にて
現代歌人協会賞授賞。
エッセイ、小説、絵本も手がけ、
著書多数。