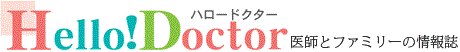世界で活躍できる研究者の育成を
三重大学副学長(学長特命、2022年3月まで)
島岡 要 先生
世界で活躍できる研究者をいかに育成するのか――。かつて「科学立国」として世界を牽引した日本はいま、科学技術とハイテク産業の凋落が著しい。経済の停滞にとどまらず、イノベーションの喪失の原因として大学や企業の基礎研究の軽視があげられている。では、どのようにすればいいのか。2020年4月から3年、科学技術振興機構(JST)の『世界で活躍できる研究者育成プログラム総合支援事業』委員会・委員を務められた三重大学大学院医学系研究科(分子病態学)、島岡要教授にお聞きしました。(聞き手・池田知隆)
<世界的に活躍できる研究者育成に向けて>

医療者、研究者の育成でいまどんな関心を。
若手研究者を育てるための政府予算は多く出していただいています。ただそれが競争的資金として出されているので、旧帝国大学など一部の大学に集中する傾向が強くなっています。とてもいい研究している地方の大学がたくさんありますが、そこで博士号を取得した若い人が研究資金やポジションの獲得が難しくなっています。
それであれば、国内でなく海外で研究すればいいといわれても、米国では奨学金を獲得している学生が優先されています。やはり若手研究者の育成に向けた幅広いサポートがどうしても必要です。
多くの予算が割り当てられる国際卓越大学に東北大学が選ばれましたが、
研究資金の選択と集中が進んでいますね。
国の研究予算の集中化が過度になると、研究できる大学の数がほんのわずかになり、全体的に研究者の人口が減少し、必然的にいい研究ができる可能性も減ってきます。各大学が研究者育成のプランを提出し、それの中で優れたものを選んで予算を出すことになっていますが、採用されるのはほとんど旧帝大ばかりです。地方の大学で若い研究者をどのようにメンタリング(人材育成)していくのか。言葉でいうのは簡単ですが、具体的にどういうふうにするのか難しい。単独の大学ではなく、周りの大学や研究所と協力して若手研究者の行き来を促進するプランが多く出されています。
三重大学ではどんなことを。
大学の教務委員長として教育改革に取り組んできましたが、いまはその場を離れました。救急医療の研究と教育をやるための災害救急医療・高度教育研究センター長(現・地域災害医療リーダー育成センター)やバイオエンジニアリング国際教育研究センター代表として特に取り組んだのは、研究のプロポーザルを書くことです。プロポーザルは、企画力や提案力を表す科研(科学研究費助成)やNIHグラント(アメリカ国立衛生研究所助成金)といった研究計画書のことで、研究者として必要なプロポーザルの力をつけることが大切です。世界で活躍するには英文で、仮説に基づく研究計画を立てることが求められています。
研究者としてのライフワークは、細胞接着分子インテグリン(Integrin)に焦点を当てた免疫疾患や敗血症の病態解明です。またウェアラブルやAIを用いて医療従事者をエンパワーメントするテクノロジーにも興味を持っています。

出身はどちらですか。
県立畝傍高校です。一応進学校ですが、そんなに厳しい指導があるわけでもなく、割とおおらかでしたよ。テニス部に入りましたが、受験勉強に専念するために後半はもう辞めました。
大阪大学医学部時代は。
身体障害者支援のボランティア活動に興味があり、奈良医大の学生たちといっしょに「アート」と「ケア」の視点から、さまざまな事業を実施している市民団体「たんぽぽの家」(奈良市)で活動しました。塾の講師もして、いろんな大人の世界に興味がありましたね。大学では、生化学関係の研究室で実験の真似事を習いましたが、学部6年生の病院実習の時に、人工呼吸器につながれた重症患者を集中治療室で熱心に治療する麻酔科医の姿が恰好よく見え、麻酔科医・集中治療医を志望しました。
研修先は。
臨床症例が豊富で様々な経験を積むことができる大阪府立病院麻酔科(現・大阪府立病院機構・急性期総合医療センター)で研修しました。その後、大阪大学医学部附属病院・集中治療室でもスタッフ医師をしているうちに、新たな治療法開発のための研究への関心が高まりました。敗血症性ショックの病態、特に炎症と組織傷害のメカニズムについて研究をしようと決意ました。
大阪大学微生物病研究所にも出入りし、阪神淡路大震災では食中毒をめぐる調査に入り、被災地の保健室みたいなところでボランティア活動に加わりました。翌96年の大阪府堺市での病原性大腸菌O157による集団感染は医師調査団として病態の解明にあたりました。
大阪大学の研究のレベルは高く、留学の必要はないかなと思っていましたが、指導していただいた清野宏教授(現・千葉大学卓越教授)の勧めで海外に飛び出しました。結婚して半年後のことでした。
海外留学が人生の転機に。
バーバード大学医学部・血液研究所(現・ボストン小児病院・分子医学分野)のTimothy Springer博士の研究室でポスドクとして働きました。ポスドクの給与はわずかですから、節約、節約の日々で、当時は若くて怖いもの知らずでした。
当初は2、3年ほどで帰国し、臨床医として戻る予定でした。しかし、ある日、所内に助教授の空きポジションができたので、そこで独立してラボを持つことを勧められました。グラント(助成金)を獲得できなければ、解雇の可能性もあり、すごく迷いました。多くの方のサポートのおかげで、複数のNIHグラントを獲得し、一流誌にも責任著者として自分の名前で論文を発表することができました。
研究のレベルは阪大と大差はありませんが、研究の自由度が高かったですね。いろんな国から集まってきたポスドクたちが独立した研究室を持てるPI(Principal Investigator)を目指している環境はとても刺激的でした。

『優雅な留学は最高の復讐である』という
本を書かれておられますね。
私のボストン留学時代の愛読書『優雅な生活が最高の復讐である』(カルヴィン・トムキンズ)』に向けたオマージュです。「優雅な生活が最高の復讐である」は辛辣なスペインの諺です。ここで使われている「復讐(Revenge)」という言葉の語源は、「自らの正当性を立証する」という意のラテン語に由来します。つまり、留学とは、鮮やかな生(せい)のリアリティーを実感するなかで自分の力を試し、揺るぎのない自分を立証する優雅で贅沢な機会である、という思いをこめています。
私の場合、苦労の量としては少ないかもしれませんが、それでも足がすくむ恐怖感がありました。そこで助けてくれる人がいてなんとかなりましたが、100%安全な道はありません。政府や企業から派遣され、手厚いサポートを受けている人に比べると、ポスドクとして留学するのは経済的には恵まれず、大変です。それでもチャレンジすることの大切さを伝えたかったのです。
2008年、ハーバードビジネススクールのパートナーとバイオベンチャーを起業するがリーマンショックの余波で頓挫しました。しかし、失敗しても命まで取られないことを学びました。
ハーバード大学で13年間も過ごされたのですね。
言葉も通じない異国の地でゼロから生活や仕事を始めるなかで、鮮やかな生のリアリティーを実感することができました。さらに自分の実力の何十倍もの仕事を達成できました。日本に蔓延する同調圧力としての空気から解放され,いい意味で空気を読まない力を身につけました.
でも、残念ながら、アメリカの“選択の自由という呪縛”に疲れたのも事実です。アメリカではたくさんの選択肢があり、主体的に自分で選ぶことで自由を行使することが正しいという価値観が君臨しています。関西で普通の日本式教育を受けて育った私は、選択するのが面倒臭いと思うし、選択の結果としての責任を負うことにもストレスを感じます。例えば、レストランでも肉の焼き具合、サイドメニューやワインの選択などは、料理はすべて大将のお任せでお願いしたい、と思うほうです。
選択肢は複数あります。そのうちのひとつを自由意志により積極的に選ぶというのは欺瞞です。人は重大な選択を迫られ、そのなかで否応なしに選択をするのが自然の姿です。数字で表しきれない価値観に関する選択や判断は理性ではなく、感情により行われます。人は理性的であろうとし、最後まで選択を粘りますが、所詮理性には価値判断をする力はないので、最後は感情に任せるしかありません。
<研究者人生について>
三重大学に赴任していかがでしたか。
ハーバード大でのインテグリンの研究実績をもとに三重大学に赴任しましたが、私の研究の原点はやはり敗血症です。そのうちに、麻酔薬のうちの1つがインテグリンに結合し、その活性化を阻害することがわかりました。多岐にわたった私の研究がしっかりと結合していったのはうれしかったですね。
救急医療と敗血症ショックにも力を注がれていいますね。
敗血症性ショックというのは、急激に病態が変化します。細菌感染が全身に広がって、自分の免疫が過剰に活性化されるために組織が傷害され、血圧が下がってショック状態になります。2019年にはショック学会長を務めましたが、出血した時に、循環血液量が減ってショック状態になる研究している人もいるし、虚血再灌流障害といって、血流が一時的に抑制された後に血流が再開された際に、組織や細胞に損傷が生じるタイプのショックの研究もあります。敗血症性ショックは集中治療室では死因の1位を占め、救急医療のときには、ショックの研究は欠かせません。
どのような研究室ですか。
私の研究室の公用語は英語です。「英語でコミュニケーションできる」というので海外からの留学生が割と来てくれます。タイ、ガーナ、ミャンマー、中国などいわゆる発展途上国からが多いですね
近年、臨床研修制度が整備され、また学会主導の専門医制度が充実するにつれて、時間を研究のために割くことが難しくなっています。日本では医学部卒業から定年までに約40年しかありません。臨床も研究も全力投球し、家族とも向き合う時間を確保するには時間が足りないのです。
近視眼的に損得勘定でキャリアをみれば、研究医の道を歩むことは必ずしも得ではないかもしれません。また研究医が万人に向いているわけではないのも事実です。このような現状が研究医になる医師の数が増えるのを妨げています。
しかし考えてみてください。希少性のあるキャリア選択はそれ自体価値を生みます。いまこそ研究医の希少性に注目し、その希少性を活かしてほしいと思います。
基礎研究を広げるための課題は。
基礎研究は何に繋がるかは、最初のうちははっきりしませんが、国のイノベーションを起こすという点ではすごく大切です。海のものとも山のものとも分からない研究が100個ぐらいあって、そのうちの1つが実際の世の中の直接役に立つようなものにつながるような確率かもしれません。それでも母数がある程度ないと実を結ばず、イノベーションが起こりにくくなります。チャレンジする人を多く育てることが大事です。
それともう1つは、チャレンジすると必然的に失敗する人も増えてきます。その時の失敗の受け皿が日本には少ない。アメリカでPIを目指しても、なれない研究者が半分以上いますが、その受け皿として製薬会社やベンチャー企業などがあります。そこでも基礎研究に力を入れていて、待遇もよく、流動性も高い。それで普通に幸せに暮らしている人もたくさんいます。
具体的に医学教育については。
いま、医学部に入った学生の大部分は臨床医になりたいと思っています。学年が上がるにしたがって、医学研究に目が行きにくい状態にあるといえます。その中で効率的に研究し、博士号を取得できるシステムの構築や基礎医学の教室がうまく立ち会えればいい。
ここでは教授1、准教授1、助教1の3人体制です。これでも少ないぐらいなのに、これが2人体制になる可能性もあります。大学改革と称して基本的な研究資金が減らされ、人員も経費も削減されています。常勤の人員が少ないのが、基礎医学が先細りする原因の1つです。
地方の中堅の大学ではなかなか特色を出すのが難しい。基本的には臨床志向で、地域医療に力を入れ、地域での医療、医師不足を補ってくれる人材の育成に注力しています。その中でも基礎研究に興味ある人がいれば、できるだけサポートしていきたいですね。
若い研究者へのメッセージを
若い研究者の中には、計画は立てているけど自信がなく、行動に移せない人がいます。その原因は、行動する前に考え過ぎるからです。どんなに考えても、未来を高い精度で予測することはできません。ならば、まず小さな一歩を踏み出してほしい。するとそこで新しい出会いや発見があります。
AI(人工知能)が普及し、英語についていえば、あまり英語力がなくてもコミュニケーションできるようになっています。いろんなSNS(ソーシャルメディア)があって情報の取り方も変わってきました。若い人にとって、海外で挑戦しやすい環境であるのと同時に、情報がすぐ得られるので海外に行かなくていいという2つの考え方があります。でも、私は、SNSやインターネットだけではなく、多彩な人と直接つきあわないとわからないものがたくさんあると考えます。
また年齢を重ねてから新しいことに挑戦するのには勇気がいります。40代以降は自分で知識を身に付けることに腐心するのではなく、まずその分野に関係するパートナーを見つけるといい。その人とよい人間関係が結べれば、そのエッセンスを学ぶことができ、自分で一から学ぶより断然効率がいい。その後、独自で新しいことを行動に移せば、結果が出てきます。
私の座右の銘は、チャーチルの「成功とは,失敗から失敗へと情熱を失わずに進む能力である」です。問題が生じれば解決しながら計画の修正をしていけばいい。それを繰り返すことで、結果的に目的を達成します。生産性や創造性をたかめる研究のための作法があります。どのような計画でも常に不完全なので微調整が必要です。チャレンジを続け、サイクルを回すのが大切です。とにかく行動しながら考え、いろんな世界、いろんな人の交流を重ねていくことが大切です。
島岡 要 先生 主な略歴
1964年 奈良県橿原市生まれ
1989年 大阪大学医学部卒業
1989年 大阪府立病院麻酔科研修医
1993年 大阪大学医学部附属病院集中治療部医員
1994年 大阪大学微生物病研究所(細菌感染、免疫化学)研究員(大学院)
1996年 大阪大学医学部、麻酔集中治療医学講座、助手(助教)
1998年 ハーバード大学医学部・ボストン小児病院麻酔科、研究員、講師、准教授
2011年 三重大学大学院医学系研究科(分子病態学)教授
2013年 同 災害救急医療・高度教育研究センター センター長(兼務)
2014年 同 バイオエンジニアリング国際教育研究センター センター長(兼務)
2021年4月 同 副学長(学長特命、2022年3月まで)
日本Shock学会・理事(2019学会長)、日本血栓止血学会、日本免疫学会、日本麻酔学会の各会員。